やさしい日本語は外国人に優しい

「やさしい日本語」
「避難してください」と言われても、外国人にとっては何を言われているのかわからないのが現状です。
この場合は「高い ところに 逃げて」と言えば理解したかもしれないと友人を亡くされた方からの声も届いているようです。
「やさしい日本語」とは
普通の日本語よりも簡単で、外国人にもわかりやすい日本語のことです。
1995年1月の阪神・淡路大震災では、日本人だけでなく日本にいた多くの外国人もたいへんな被害を受けました。
その中には、日本語も英語も十分に理解できず必要な情報を受け取ることができない人もいました。

そこで、外国人などの人が災害発生時に適切な行動をとれるように考え出されたのが「やさしい日本語」の始まりです。
そして、「やさしい日本語」は災害時のみならず、平時における外国人への情報提供手段としても研究され、法務省をはじめ出入国在留管理庁など行政情報や生活情報、毎日のニュース発信など、全国的に様々な分野で取組が広がっています。
しかし、世界にたくさんの言語がありそれぞれに応じた多言語化の実現を目指し多言語対応協議会で多言語への対応の基本な考え方を作成し取り組んでいる。
しかし、それぞれの言語の難易度があり、簡単にはいかないようです。
日本に住む外国人は
日本に住む外国人は、この30年で3倍に増え、国籍も多様化しています。
2019年末には約293万人で過去最多になりました。

その外国人が言葉のニーズとして「希望する情報発信言語」はどの言語が良いのか英語なのか日本語なんか、または母国語なのかを調査してみた。
外国人への調査「日常生活に困らない言語」を
- 「日本語」と答えた外国人は約63%
- 「英語」と答えた外国人の44%
で、大きく「日本語」が上回っています。
また、法務省による調査でも日本語で会話ができると答えた外国人は8割を超えています。
さらに、東京都国際交流委員会の調査では「希望する情報発信言語」として
- 「やさしい日本語」を選んだ人が最も多く76%
- 「英語」が68%
- 「日本語」が22%
- 「機械翻訳された母国語」が12%
- 「非ネイティブが訳した母国語」が10%
と、やさしい日本語に対するニーズが高いことがわかります。
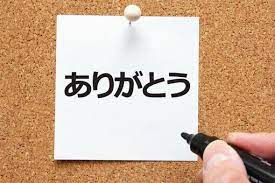
数年前に社内語は、英語と打ち出した上場企業がありましたね。
皮肉なもんですね母語を他国語に統一して会議やコミュニケーションがとれるとは、よっぽど英語にたけてる人が集まっているのでしょうね。
<参考>
世界には、137の国・地域において、約365万人の方々が日本語を学習しています(国際交流基金 2015年度「海外日本語教育機関調査」)。
また、定住外国人が理解できる言語として、「日本語」は62.6%、「英語」は44%という調査結果が国立国語研究所より示されています。日本に定住する外国人は、約230万人(2016年法務省統計)で、訪日外国人と共に増加傾向です。
「会話」で伝えるときだけでなく、看板等の「表示」によって伝えるときも同様です。
相手に外国語で伝えたい内容は、わかりやすい言葉から考えることによってより伝わるものとなります。
まず、日本人にもわかりやすい文章特に官公庁の出す文章は、われわれでも理解できないことが多いですね
- 文を短くする
- 回りくどい言い方や不要な繰り返しはしない
- 3つ以上のことを言うときは、箇条書きにする
外国人にわかりやすく

- 二重否定を使わない
「~ないことはない」「~ないわけではない」 - 簡単な言葉を使う(難しい言葉を使わない)
「こちらに記入願います」⇒「この紙に書いてください」 - 簡単な言葉を使う(難しい言葉を使わない)
- 曖昧な表現はできる限り使わない
- 文末は「です」「ます」で統一する
- 重要な言葉はそのまま使い、<=・・・>で書き換える
余震<=後から来る地震> - すべての漢字にふりがなをつけます。
など、注意点に注意して表記します。
- 災害時の情報提供としての「やさしい日本語」
- 平時の情報提供としての「やさしい日本語」
- 観光のツールとしての「やさしい日本語」
- 報道のツールとしての「やさしい日本語」
などの取り組みをしています。
各県の自治体、内閣府、多言語対応協議会気象庁などで検討会、フォーラムなど実施されています。
私たちもなるべく「やさしい日本語」を取り入れて日本人にも、外国人にも、わかりやすい生活を心がけましょう。







