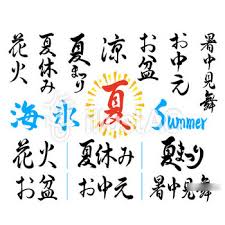小正月は行事がたくさんあります

小正月
小正月は旧暦の1月15日に立春後の望月に(満月)あたり、昔はこの日を正月としていた名残。

小正月
元日(1月1日)を大正月(おおしょうがつ)に対して1月15日に行われる行事のことをいいます。
大正月は、年神様やご先祖様を迎える行事に対して小正月は豊作祈願などの農業に関する行事や家庭的なものが多いのが特徴です。
小正月の別名は「女正月」「小年」「若年」「二番正月」「花正月」とも呼ばれている。
大正月を男正月、小正月を女正月ともいい年末から大正月、松の内の準備や行事で疲れた女性をねぎらう意味から、この日は女達だけのお正月「女正月」とした言い伝えもあります。
この日は鏡開きでもありますね。
小正月の行事
左義長
小正月に行われる火祭りの行事。
呼び名は各地でちがうものの、日本全国でおこなわれる風習です。
田や畑などに竹を3,4本組んで立て、そこにその年に飾ったしめ縄や門松、飾り物や書初めなどを燃やします。
そこから出る煙に乗って年神様が天井に帰ってゆくとされてます。
これは「どんど焼き」「どんど」とも呼ばれ、その火で焼いたお餅を食べると無病息災で過ごせるといわれる。

どんど焼き
豊作祈願の「餅花・もちばな」
餅花は商店街の軒先でよく見かける紅白の餅を柳などの木に飾り付ける風習があり、「花正月」と呼ばれる由縁です。
餅花のほかにも下記のようなものもあります
- 「稲の花」枝垂れ柳の枝で稲穂を表す
- 「繭玉・まゆだま」米の粉を繭の形にした
- 「花餅」花の形に作った小さな餅を枝に刺す
- 「だんご木」ミズキ(だんご木」の枝に紅白の団子に、鯛・小判・打ち出の小槌などをかたどったフナせんべいをつける。
- 「粟穂稗穂・あわぼひえぼ」カズの木(ヌルデ)を短く切り皮をむいたものと向いてないものを割り竹に刺してたばねたもの。
これらの飾り物は1月15日までには外すようです。
小豆粥(あずきがゆ)
小正月には小豆粥を食べて無病息災を祈ります。
小豆のような赤い食べ物は邪気を払うと考えられていた中国の古い風習に由来しているそうです。
「枕草子」や「土佐日記」にも小豆についての記述があるほど伝統的です。
だから、お祝い事には小豆を使った赤飯が食卓に出てくるわけですね。
粥占い
小正月には、豊作祈願をお粥でその年の農作物の豊凶や天候、世相を占う「粥占い」が行われます。
神社が行う行事で「粥占(かゆうら)神事」「筒粥(つつがゆ)神事」などと呼ばれ今でも各地の神社で受け継がれています
おぜんざい
小豆粥の代わりとしておぜんざいを食べる地域もあります。
子供のころは鏡割りした鏡餅を入れて食べてました。

おぜんざい
その他にも地方では
- 「鳥追い」田畑を荒らす鳥を追い払う
- 「もぐら追い」もぐらを追い払う
- 「えんぶり」1年の豊作を祈願して祈る
- 「なまはげ」東北地方の正月行事
怠け者をいさめるため家々に鬼がやってきて「悪い子はイネ~か」「泣く子はイネ~か」などと大声を出して回ってきます。
以前は小正月の行事でしたが現在は大晦日に行われています。
- 「かまくら」
雪のほこらを作り、祭壇を設けお参りしたり子供たちがその中で火をともして遊びます。
昔は「元服の義」を小正月に行ってました。
そのことから1月15日は「成人の日」として国民の祝日になりました。
この成人の日と小正月の関連がわかりづらくなり「成人の日」は1月の第二日曜日に変更されました。
大正月・小正月の行事は地域でさまざまですが、希望の一年のスタートを気持ちよく過ごしましょう。
参考:気になる話題、Wikipedia、暮らし歳時記、ジャラン、